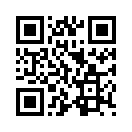■ 記事掲載のお知らせ ■
『雨漏り診断・修理』についての当社取り組みです
日経ホームビルダー2011.1号より連載開始
写真でわかる『雨漏りを呼ぶ納まり』
玉水先生とともに監修を行いました
2011.6号 記事紹介はこちらへ
2011.4号 記事紹介はこちらへ
2011.3号 記事紹介はこちらへ
2011.2号 記事紹介はこちらへ
2011.1号 記事紹介はこちらへ
『雨漏り診断・修理』についての当社取り組みです
日経ホームビルダー2011.1号より連載開始
写真でわかる『雨漏りを呼ぶ納まり』
玉水先生とともに監修を行いました
2011.6号 記事紹介はこちらへ
2011.4号 記事紹介はこちらへ
2011.3号 記事紹介はこちらへ
2011.2号 記事紹介はこちらへ
2011.1号 記事紹介はこちらへ
塗装・防水・雨漏り修理/当社HPメニューはこちらから
はじめてご覧頂く方へ|塗装について|雨漏りについて|シーリング(コーキング)について
実録!! 信頼とは何か?|雨漏り調査・診断について|ごあいさつ|お問い合わせ
はじめてご覧頂く方へ|塗装について|雨漏りについて|シーリング(コーキング)について
実録!! 信頼とは何か?|雨漏り調査・診断について|ごあいさつ|お問い合わせ
2014年02月06日
雨水の影響
先日から工事をスタートさせた、とある塗り替え現場。
築18年で初めての工事となり、屋根や外壁の痛み度合いは、それ相応の状態。
このそれ相応と言う曖昧な表現は、非常に判りにくい言い方なのだが、簡単に言えば、塗り替えは出来るが、それなりにコストが掛かると言う意味である・・・・・。
しかし、何も好き好んで放置していた訳ではなく、それぞれのお宅においての都合やタイミングなど、様々な要件が重なっていくのですから、私としては、目の前の建物に対し、出来るかぎりの手を施すだけなんです。
今回の現場も、外壁の割れたサイディングを交換し、あとは、最適な塗料の選定や、工程や塗り回数を増やすことで、工事を進めようとしていたのですが・・・・・。
屋根・外壁の洗浄を終えて、外壁のサイディングを交換すべく職人と現場へ入り、割れたサイディングを剥がすと、そこに現れたのは、通常の光景とは、まったく異なるもの。

サイディングを剥がす際、妙な柔らかさがあり、「あれ??」と思ったのですが、その中にあったのは、蟻の巣と化した柱!!!

「やられた・・・・・」
工期延長決定!!(涙)
とりあえず、蟻の巣となってふかふかと盛り上がっている木屑を崩していくと、中から蟻は発見されず、原型を留める部分が僅かとなっている柱はともかくとして、土台は何とか形を残している。
幸い(?)にも、このような形となっているという事は、雨水などの影響を疑うのですが、今回、その原因としての最有力候補は、スグ目の前に出てきたのです。
それは、後付けのアルミ製バルコニー。
洗浄前に起きていなかった事象である、水の流れ、洗浄後3日を経過しているにも関わらず、バルコニーの奥桁部分より、水の流れが確認できたのである。

まさかまさか、奥桁部分から水がヒタヒタと流れるとは・・・・・。
既製品の床ジョイントとなる桁部分に落ち葉や、洗濯物などからでる綿ホコリや糸くずなどが溜まり、そこに水が入ると、ヘドロのような状態なることがあるのは確か。
しかし、そのヘドロ掃除してからも何か違和感を覚えたため、桁部分に水平器を当ててみると、何と!逆勾配となっていたのです!!
「いや~、やられた!!!」
もちろん、バルコニーを撤去し、外壁を剥がしていかないと、これが根本原因かどうかの確証は無いのですが、それにしても、柱が無くなるまでとは・・・。
雨水の影響はこのような酷い現象を起こしてしまうし、もっと根本的に言えば、建物の雨仕舞においての問題としか言いようが無いのですが、蟻の巣が壁内からというケースは、ウチの工事でも、年1回までは無い。
言うなれば、室内へは出ない雨漏りである。
さて、また自分で行う大工工事が増えたなぁ・・・・・と、現場と工程のやりくりに頭を悩ます内容が増えたのです。
築18年で初めての工事となり、屋根や外壁の痛み度合いは、それ相応の状態。
このそれ相応と言う曖昧な表現は、非常に判りにくい言い方なのだが、簡単に言えば、塗り替えは出来るが、それなりにコストが掛かると言う意味である・・・・・。
しかし、何も好き好んで放置していた訳ではなく、それぞれのお宅においての都合やタイミングなど、様々な要件が重なっていくのですから、私としては、目の前の建物に対し、出来るかぎりの手を施すだけなんです。
今回の現場も、外壁の割れたサイディングを交換し、あとは、最適な塗料の選定や、工程や塗り回数を増やすことで、工事を進めようとしていたのですが・・・・・。
屋根・外壁の洗浄を終えて、外壁のサイディングを交換すべく職人と現場へ入り、割れたサイディングを剥がすと、そこに現れたのは、通常の光景とは、まったく異なるもの。
サイディングを剥がす際、妙な柔らかさがあり、「あれ??」と思ったのですが、その中にあったのは、蟻の巣と化した柱!!!
「やられた・・・・・」
工期延長決定!!(涙)
とりあえず、蟻の巣となってふかふかと盛り上がっている木屑を崩していくと、中から蟻は発見されず、原型を留める部分が僅かとなっている柱はともかくとして、土台は何とか形を残している。
幸い(?)にも、このような形となっているという事は、雨水などの影響を疑うのですが、今回、その原因としての最有力候補は、スグ目の前に出てきたのです。
それは、後付けのアルミ製バルコニー。
洗浄前に起きていなかった事象である、水の流れ、洗浄後3日を経過しているにも関わらず、バルコニーの奥桁部分より、水の流れが確認できたのである。
まさかまさか、奥桁部分から水がヒタヒタと流れるとは・・・・・。
既製品の床ジョイントとなる桁部分に落ち葉や、洗濯物などからでる綿ホコリや糸くずなどが溜まり、そこに水が入ると、ヘドロのような状態なることがあるのは確か。
しかし、そのヘドロ掃除してからも何か違和感を覚えたため、桁部分に水平器を当ててみると、何と!逆勾配となっていたのです!!
「いや~、やられた!!!」
もちろん、バルコニーを撤去し、外壁を剥がしていかないと、これが根本原因かどうかの確証は無いのですが、それにしても、柱が無くなるまでとは・・・。
雨水の影響はこのような酷い現象を起こしてしまうし、もっと根本的に言えば、建物の雨仕舞においての問題としか言いようが無いのですが、蟻の巣が壁内からというケースは、ウチの工事でも、年1回までは無い。
言うなれば、室内へは出ない雨漏りである。
さて、また自分で行う大工工事が増えたなぁ・・・・・と、現場と工程のやりくりに頭を悩ます内容が増えたのです。